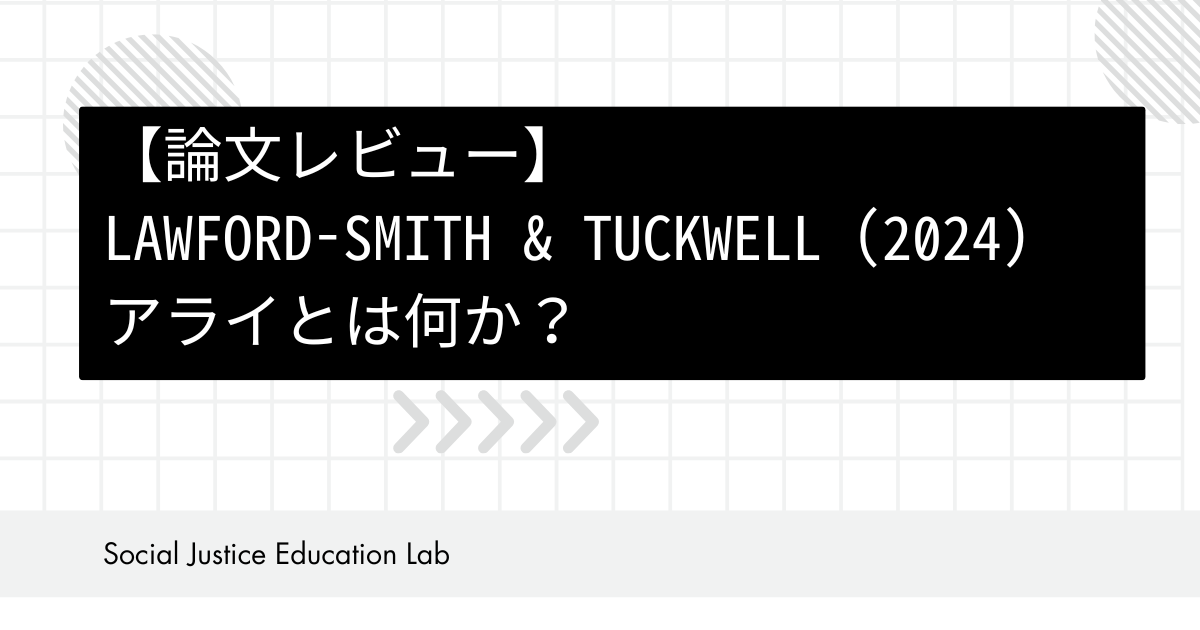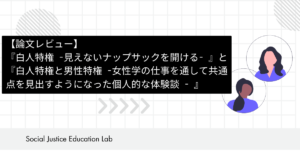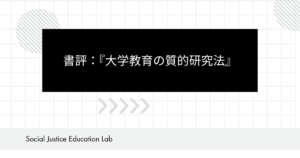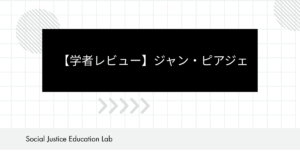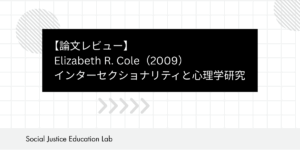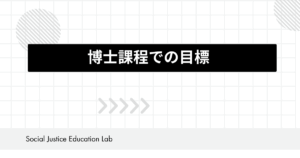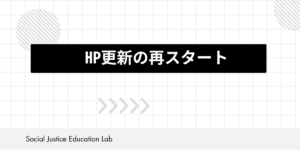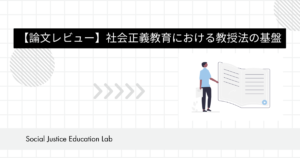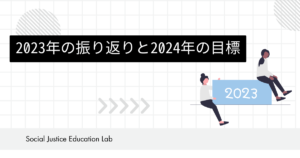はじめに
今回はLawford-Smith & Tuckwell (2024)の”What is an ally?”という論文の内容を紹介します。この論文を紹介する理由は、この論文がアライの定義を哲学的に考察している数少ないものの中の一つだからです。この論文の筆者らも論文中で述べている通り、これまでアライの定義について検討する哲学分野の論文はほとんどありませんでした。「アライシップ(アライであること)と連帯の違いは何だろうか?」等の疑問を前々から持っていた自分としては、政治哲学的な議論を期待しつつこの論文を読み始めました。
この論文の内容
この論文の課題意識
現代の社会運動において、「アライ」という言葉は日常的に使われるようになりました。大学や行政、企業がアライ研修やネットワークを制度化する例も増えており、アライであることは、善き市民性や社会的責任を体現する「徳」の一つのように扱われています。
一方で、「アライ」とは何かという問いには明確な答えがなく、むしろアライという言葉の濫用や空文化が問題視され始めています。例えば、レインボーバッジをつけながら差別的な発言をする事例や、SNSで被抑圧集団を支援する表明をしながら現実の行動を伴わない事例など、「見せかけのアライ(performative ally)」という批判を浴びる事例も頻繁に見られる様になりました。
こうした問題を背景に、Holly Lawford-SmithとWilliam Tuckwellによる本論文「What is an ally?」(2024)は、アライという語の哲学的定義を提示し、それがどのような条件下で正当化されうるのか、またいかに区別可能な社会的カテゴリーであるかを論じています。
アライの事例からアライの構成要件の導出
著者たちは、アライとして社会的に承認されてきた3つの事例をまず提示しています。それらは、1968年メキシコオリンピックにおいて黒人選手に連帯した白人選手ピーター・ノーマン、19世紀に女性の権利拡大を唱えた哲学者J.S.ミル、トランスジェンダー擁護の主張を展開した作家グレアム・リネハンです。
これらの事例から共通要素を抽出し、著者らはアライであるために必要な4つの構成要件(desiderata)を提示しています。
- 軸特定的な特権性(Axis-specific privilege)
アライは支援する集団に対して、ある社会的軸(性別、人種、階級など)において特権的な立場にある必要がある。 - 抵抗的行動(Well-founded resistant action)
抑圧構造の存在を認識し、それを減少させる方向の行動をとっていること。 - 承認(Authorization)
被支援集団によって、その行動が歓迎・認可されていること。 - 影響力(Social influence)
社会的に意味のある変化を引き起こしうる位置・影響力を持っていること。
これらの要素を同時に満たすことによって、アライというカテゴリーが妥当性を持つと著者らは主張しています。
アライの定義
上記の要件をもとに、著者らはアライを以下のように定義しています。
「個人Iが集団Gに対するアライであるのは、IがGと同じ軸において特権的であり、Gの抑圧を軽減するために適切に承認された抵抗的行動を、Gへの適切な敬意をもってとるとき、かつその行動がGの利益を向上させることを目的とする場合である。」
抵抗的行動の条件:信念ではなく実践
ここから筆者らはアライの構成要件一つ一つの検討に移ります。本論文の重要な論点の一つは、「アライシップは信念や態度ではなく、行動によって特徴づけられるべきである」という主張です。つまり、どれほど善意であっても、それが可視的で、実践的な介入として現れない限り、アライとは呼べないということになります。
著者らはこの点を、以下の三つの視点から掘り下げています。
- 失敗可能性と誠実性:アライによる行動が、結果的に誤解や不適切な介入になる可能性は否定できません。たとえば、特定の言説が抑圧的であると認識し、代替的な表現を試みても、それが別の形で問題視されることがあります。しかし、著者らは、そうした行為の「結果」ではなく「意図の誠実さと調査の程度」を重視します。言い換えれば、一定の批判に晒されても、事前に十分な配慮と情報収集がなされていた場合、それはアライ行動と見なされうるのです。
- 単発的 vs 継続的行動:しばしばアライであることは「持続的コミットメント」であると理解されがちですが、本論文はそれを必須条件としません。一度限りの行動であっても、特定の社会的文脈において意味を持つ場合にはアライ関係が成立しうるとしています。もちろん、継続的実践の方がより強固な関係性と信頼を築きやすい点は認められますが、定義上は必須ではないという柔軟性が示されています。
- 被支援集団の目標との整合性:行動がアライとして評価されるためには、単に「善意」であることでは不十分で、それが被支援集団の政治的・社会的な目標と一致するものでなければならないとされます。例えば、フェミニズム運動の中でも急進派とリベラル派で求める戦略が異なる場合、アライ行動の評価も分かれる可能性があるわけです。
この議論の背景には、Ferracioli & Terlazzo(2021)が提唱する**「フェミニスト的行動主義(feminist activism)」**の概念があります。これは、特権を持つ個人が、単なる信念表明にとどまらず、現実に不平等を是正するために政治的行動をとることが倫理的に要請されるという考え方です。本論文は、この立場を引き継ぎつつ、アライシップの定義にその実践的側面を組み込んでいます。
承認の重要性:誰が「アライ」と認定するのか
アライの正当性は、単に行為者の主観的意図や宣言によってではなく、被支援集団の承認によって裏付けられなければならない――これが本論文の中心的主張の一つです。
しかし、ここで問題となるのは、「誰がその集団を代表して承認するのか」「どのような承認が正当なものとされるのか」という問いです。集団は一枚岩ではなく、しばしば内部に対立や多様な意見が存在します。そのため、承認のあり方を以下のように区別しています。
- デフォルト承認(default authorization):これは、集団内部である程度の合意が取れている社会的要求、政治的目標などに沿った行為に対しては、明示的な承認を受けていなくても「黙示的に承認されている」とみなせるという立場です。たとえば、公共空間での差別発言に対して抗議する行為や、包括的セクシャル・マイノリティ教育の導入を支持する発言などは、多くの運動内部で共通認識されている要求に沿っているため、明示的な「承認」がなくてもアライ的とみなされる可能性があります。
- 明示的承認(explicit authorization):一方で、運動内部で意見が分かれている問題(例:トランスジェンダーのスポーツ参加など)については、特定の代表や運動のリーダーからの明示的な支援要請があった場合に限り、アライ行動と認定されうるとされます。ここで著者は、「代表性」を持つ構成員(activist leaders, spokespeopleなど)に着目し、集団全体の一貫した同意を要件とする立場を取らない点が実践的です。
この承認概念は、パターナリズムや傲慢な介入の危険性を回避する仕組みとして設計されており、アライ行動を一方的に「良いこと」と見なす傾向への警鐘となっています。
適切な敬意の在り方:盲信と懐疑のあいだで
この部分は、アライが被抑圧集団のメンバーに対してどのような認知的・倫理的態度を取るべきかという問題に関する議論です。とくに、以下のような問いが中心です:
- 被抑圧者の証言をどの程度信頼すべきか?
- 敬意を表すとは具体的にどういうことか?
- 検証や懐疑はいつ、どのように許容されるのか?
この問題をめぐって、Kolers(2016)やMcKinnon(2015)は、「deferential trust(服従的信頼)」を支持しており、特に非特権者の経験や声を優先的に扱うことをアライの条件として強調してきました。しかしLawford-Smith & Tuckwellはこの立場に批判的です。なぜなら、全面的な服従や盲信は以下のような危険を孕むからです。
- 道徳的主体性の放棄:アライが他者の証言に全面的に従うことは、自らの倫理的判断力を放棄することに等しく、それはむしろ非倫理的になりうる。
- 議論空間の閉鎖:意見の多様性や批判的検討が忌避されることで、知的・政治的な停滞や排除が起こるリスクがある。
- 偽の連帯とポジショナルパフォーマンス:無条件の信頼を示す行為が、真の関係性や連帯ではなく、承認欲求や見せかけの倫理的優越性に基づくパフォーマンスとなりうる。
その代替として著者らが提唱するのが、「価値反映的理由(value-reflecting reasons)」に基づく選択的敬意です。つまり、アライは他者の声を原則的に尊重しつつも、それが自らの倫理的枠組みと合致するかを吟味し、相互的な責任倫理のもとに信頼を構築すべきだと主張しています。
7. アライシップの社会関係論:階層性とその解消をめざして
アライ関係は、構造的には非対称です。つまり、特権的立場にある者が、抑圧された他者を支援する構造をもつものです。しかしその最終目的は、特権と抑圧という前提自体を解消することにあります。つまり、以下がアライとは何かを考える上で重要になります。
- アライ関係は恒常的なものではなく、「過渡的」かつ「終焉を志向する関係」である。
- アライシップの成功とは、自らの必要性を無くすことにある。
この考え方は、アライを自己目的化しないというスタンスに則っています。
9. 結語:アライ概念の制度的・実践的応用へ向けて
この論文は、アライを単なる流行語ではなく、哲学的概念として再定義することを試みています。その意義はまとめると以下のようになります。
- アライの行動と関係を中心に置くことにより、アライというものを評価・判断できるようにする。
- 被支援集団の視点を尊重しつつ、アライ自身の倫理的判断も保持する中庸的立場を確立する。
- アライシップの誤用や悪用を防ぐ規範的枠組みを提供する。
最後に
この論文で提示されたアライの構成要素についての議論は大変勉強になる内容で、とても興味深く読むことができました。一方で、アライの定義については検討が不十分だと感じてしまいました。というのも、著者らは3人のアライと言える人物の事例から帰納的にアライの定義を導いているのですが、このプロセスに妥当性を感じません。これだと事例の選び方で定義が変わってしまうため、検討が不十分だと言わざるをえないのではないかと感じました。分析哲学でよくあるような概念定義の書き方をしているのですが、検討プロセスはあまり分析哲学のような厳密さはなく、あくまで表面的な検討という印象を受けてしまいます。
とはいえ、哲学的な議論が不足しているというこの論文の課題意識はとても重要なものに感じます。この論文が行ったような議論について引き続きチェックしていきたいと思います。