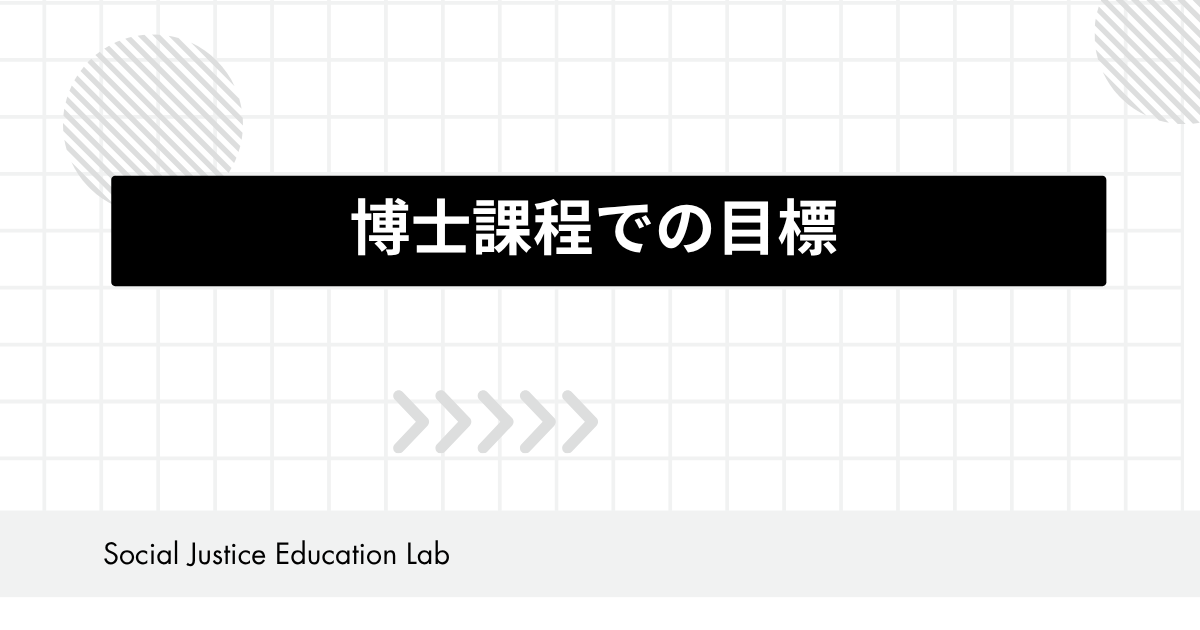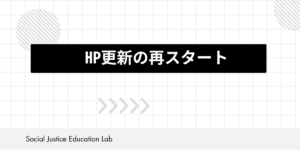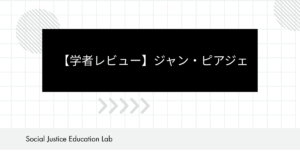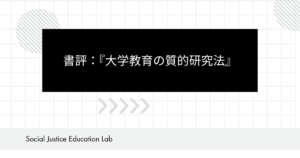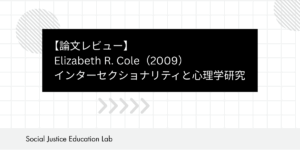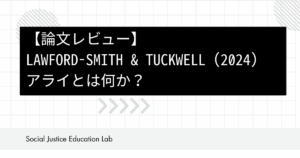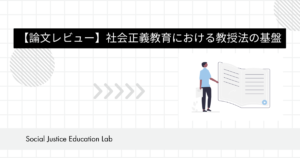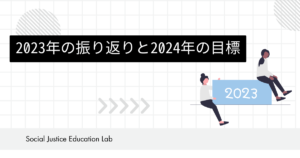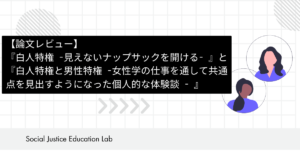無事に3月末で東京大学大学院学際情報学府文化・人間情報学コースの修士課程を修了し、同コースの博士課程に進学しました。所属研究室は変わらず山内祐平先生の研究室です。
修士課程で執筆した修士論文『証言的対話に基づいたアライの教育プログラムの開発』はコース長賞をいただくことができました。ただ、大変光栄に思うと同時に、M2の特に後半は思いがけない理由で安定して研究に取り組めなくなってしまった時期もあり、もっと上手く書けたのではないかというやりきれなさを感じています。今抱えている不全感を乗り越えるためにも、博士課程ではより一層懸命に研究に励みたいと思います。
さて、すでに博士課程は始まっていますが、改めてここで博士課程での目標を書いておきたいと思います。全部で5つあります。
① 4年で修了する
修士課程2年、博士課程3年が基本とされますが、博論を書き上げて博士課程を修了するまでの年限は伸び伸びになってしまう傾向にあります。学際情報学府文化・人間情報学コースでは『文化・人間情報学研究法Ⅴ』という授業があり、最初の授業で博士課程での過ごし方について講義があるのですが、担当の山内先生曰く、3年で修了することはかなり難しく、4年修了を目指すのが現実的とのことでした。
博士課程では、博論の執筆開始までに査読付き論文を最低2つ通す必要があります。また、将来大学の教員になるためには大学で教えた経験が必要なため、多くの人が大学の非常勤として教え始めます。もちろん、研究者としてのステップアップも必要なので、修士課程と同じように研究法などの授業を履修したり、研究会に参加することもあります。何が言いたいかというと、博士課程では修士課程の時よりもより一層マルチ・プロジェクト状態になりがちであり、それが多くの人が博士課程の修了に4年以上かかる原因となっているということです。
ただ、NPO法人で事業部長として働いていた自分としてはマルチ・プロジェクトの管理はむしろ得意分野で、なんだかワクワクするな・・・とさえ思っています。とはいえ、博論執筆はもちろん自分にとって未知の頂き。簡単に踏破できるものでは決してありません。そのため、第一の目標として師匠の山内先生の教えに従い「4年で修了する」という目標を掲げました。
② Greatな博論を書き上げる
博士課程のゴールはもちろん博論を書き上げることです。ただ、自分としては、自分が専門とする領域に大きな影響を与えるような博論を書き上げたい・・と不遜ながらも企んでいます。
かつては博士号なんて簡単に授与されるようなものではなく、学問分野によってはキャリアの晩年に差し掛かってようやくもらえるもの・・・ということもあったようです。ただ、現在は博士号の授与のハードルは以前よりも下がっており、大学も国も博士人材をより多く輩出する方向に舵を切っています。実際、「博論はあくまで修作。とにかく書き上げて、早くプロの世界に入って、そこで揉まれてステップアップしていくのが良い。」と教授が博士課程の学生に声をかけているのを時折聞きます。
それはその通りなのですが、やはり取り組む限りは素晴らしい仕事をしたいと思うのは仕方がないこと。私が研究としているアライというテーマは近年注目されつつあるテーマなのですが、まだまだ分野として未成熟です。研究分野としての成熟を促すような、そんな研究を博論として世に出したいと思っています。
③ 査読付き論文を4本以上通す
博士課程の修了に必須なのは2本の査読付き論文です。私が所属するコースでは、通常は修論の研究で一本、そして博士課程になってから進めた研究でもう一本書くものとされています。ただ、もちろんこれは2本しか書いてはいけないという話ではありません。修論研究から量的データをベースに1本論文を書きつつ、レビュー部分で1本、そして質的データをベースにもう一本投稿論文を書き上げたいなと考えています。
プロの研究者という自覚を持って、アウトプットをどんどん作成し、学会誌に載せられるようにしたいです。論文を書くという作業を通じて研究者として成長しつつ、自分が著した論文を通じて多くの研究者と繋がりを作れるようにしたいと考えています。
④ 量・質両面で研究法に熟達する
修士課程で師匠の山内先生に言われたことで印象的だったのが「量と質の両方の研究法ができる研究者を目指した方が良い」という言葉でした。その時の自分はかなり意識が質的研究法に向かっていたのですが、山内先生と話して「量で何ができるのか知らないままに質にだけ拘ってはもったいないな。」と思うようになりました。そして、この確信は修論研究を通じて自分が得たデータと向き合う中で深まっていきました。
「量か、質か?」のような不毛な対立に与せず、新規性と意義がある問いと真摯に向き合うために都度適切な研究法を選ぶことができる研究者=社会科学者でありたいと今は思っています。現実的には、博士課程を修了するまでに、山内研のゼミにおいて量的研究でも質的研究でも誰よりも適切にコメント・フィードバックできる存在を目指したいなと考えています。
⑤ 将来を見据え、自ら研究会を主催する
どんな将来を見据えているかというと、学会を設立するという将来です。教育領域で社会正義に関わる研究をしている人が集う学会を作りたいです。修士課程の時に研究相談をさせていただいた学外の先生には「興味関心がある人はいるのだけれども、現在は複数の学会に別れていて、交流の機会がそれほどないかもしれない」と言われたことがあります。現時点では、北米でSocial Jusitce Educationと言われるような研究をしている人も、日本の学会だと投稿先でしっくり来るところが見つかりにくいのではないかと思うのです。
そんな将来を見据えつつ、まずは研究会という単位からスタートできればと思っています。とにかく、小さな単位からでも始めなければ現実は動いていきません。少しずつ仲間を集めながら、みんなで一緒にビジョンを描いて理想の未来に近づいていきたいものです。
最後に
博士課程も修士課程と同じく研究者としての修行期間かもしれません。ただ、査読付き論文を通すことを求められるなど、本格的に「プロとして研究すること」が求められるようになります。前職を辞めて研究者を志した時に見据えていたステージにいよいよ入りました。より一層頑張っていきたいと思います。