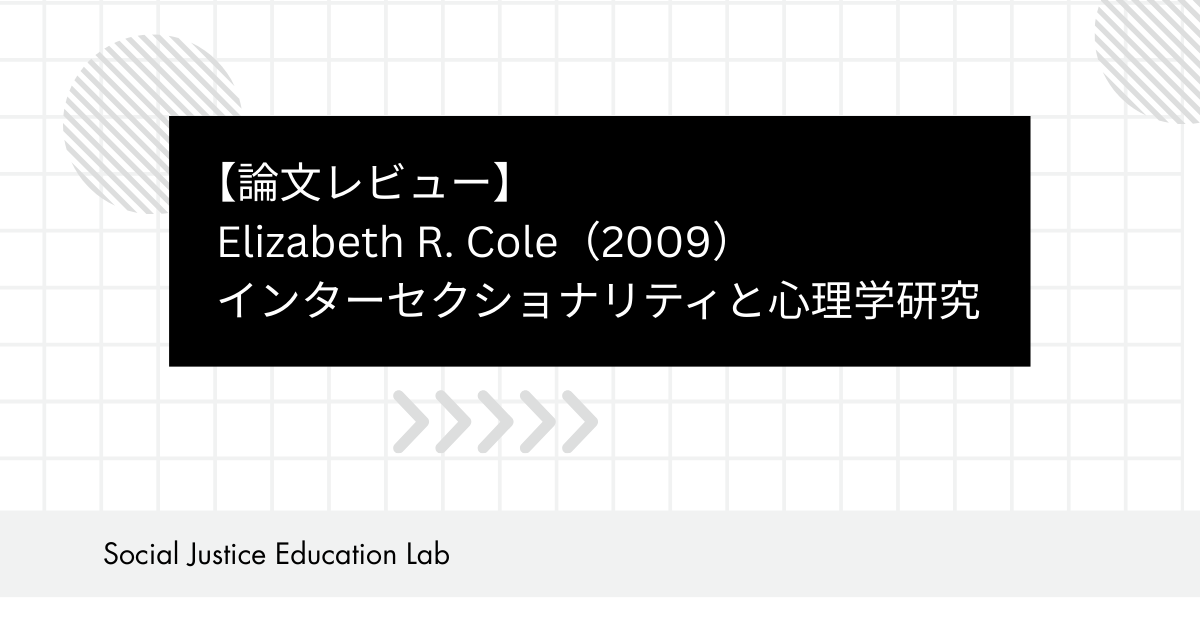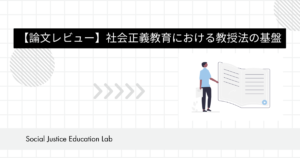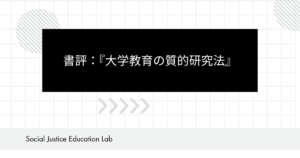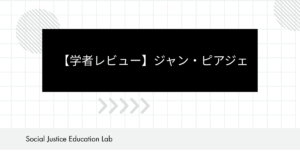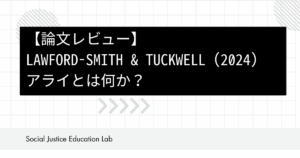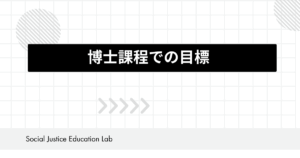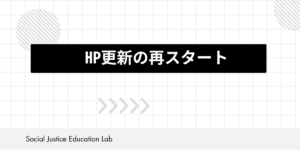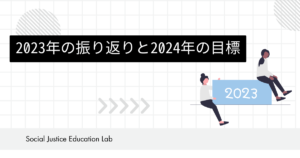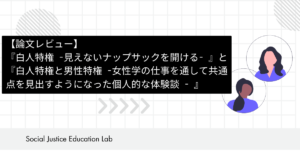はじめに
今回はElizabeth R. Cole(2009)Intersectionality and Research in Psychologyという論文を紹介します。4500件ほど引用されている論文であり、心理学分野だけでなく量的研究を行う分野にインターセクショナリティ概念を導入していく方法を考える上で重要な先行研究です。
この論文の内容
はじめに:交差性の視点はなぜ心理学に必要か
Elizabeth R. Cole(ミシガン大学)の論文”Intersectionality and Research in Psychology”は、心理学における「インターセクショナリティ」の理論的枠組みとその応用可能性を詳細に論じた研究です。インターセクショナリティとは、複数の社会的カテゴリー(人種、ジェンダー、階級、セクシュアリティなど)が相互に交差し合いながら、差別や特権の構造を形づくっているという理解に基づく分析枠組みであり、フェミニズムや批判的人種理論の文脈で発展してきました。
心理学では、社会的カテゴリーを独立変数として単独で扱う傾向が強く、カテゴリー間の相互作用や構造的背景に目を向ける試みは限定的でした。Coleはこの点を批判し、交差性の視点を導入することで、心理学の理論構築・方法論・解釈のすべてにおいて、より豊かで現実に即した分析が可能になると主張します。本論文では、理論的背景に始まり、研究設計の各段階における応用、具体的な実証研究の紹介まで、様々な議論が展開されています。
インターセクショナリティの系譜と定義
冒頭で、インターセクショナリティという概念のルーツがCombahee River Collective(1977/1995)の声明にあることが確認されます。また、Kimberlé Crenshaw(1989, 1993)は、法制度やフェミニズム理論、人種差別撤廃運動が単一の軸(例えば「性別」や「人種」)でしか差別を捉えてこなかったことを批判し、黒人女性が経験する差別がそれらの単なる足し算では説明できないことを指摘しました。
この「インターセクショナリティ」の着眼は、単にマイノリティの特殊性を理解するための道具ではなく、すべての人が同時に複数の社会的位置にあるという前提から出発し、従来の分析枠組みそのものを問い直す理論的転回であるとColeは位置づけます。
三つの問い:心理学における交差性導入の戦略的提案
Coleは、心理学研究者が交差性を研究に取り入れるための出発点として、以下の三つの問いを提起します。
- 「このカテゴリーには誰が含まれているのか?」(Who is included within this category?)
この問いは、カテゴリー内部の異質性に目を向けるものであり、サンプリングの政治性、すなわち「誰がデータに含まれ、誰が除外されているのか」という問い直しを促します。たとえば、大学生サンプルに偏る心理学研究においては、しばしば白人中産階級の女性が「女性」の代表として扱われてきましたが、これは貧困層や有色人種の女性の経験を不可視化するものです。Coleは、誰が研究対象として想定され、誰が黙殺されているのかを問い直すことによって、カテゴリーの意味そのものを考える必要性を示します。 - 「不平等はどのような役割を果たしているのか?」(What role does inequality play?)
この問いは、社会的カテゴリーを単なる記述的ラベルではなく、特権や抑圧の歴史的・制度的構造の一部として捉える視点を提供します。たとえば、白人女性のフェミニズムと黒人女性のそれとでは、伝統的フェミニティに対する態度やその政治的意味が異なると指摘されます(Cole & Zucker, 2007)。このように、同じカテゴリー内の意味の違いは、社会構造的文脈を加味しなければ理解できないものであり、心理学が構造的不平等に着目する必要性を示しています。 - 「どこに共通点があるのか?」(Where are there similarities?)
この問いは、カテゴリー間の「違い」に注目するだけでなく、「横断的な共通点」や「共闘可能性」に注目する視点です。Coleは、例えば白人労働者階級男性と黒人中産階級男性が「特権の喪失感」や心理的ストレスを共有している可能性に着目し、そこに制度的文脈や共通の位置取りを見出します。こうした共通性を見出すことで、カテゴリーに固着した差異化思考から脱し、より包括的な理解を目指すことができます。
研究への含意
インターセクショナリティを心理学の研究に応用することは、単に既存の分析モデルに「ジェンダー×人種」といった交互作用項を加えることではありません。Coleはこの点を強調し、交差性の導入とはむしろ社会的カテゴリーの意味を再構成する認識論的転換であると主張します。この視点を受け入れることで、従来の個人差モデルでは捉えきれなかった構造的抑圧のメカニズムや交錯した経験が見えてきます。
たとえば、黒人女性が経験する「人種化されたセクシャルハラスメント」は、単に人種差別と性差別の和ではなく、その複合的交錯性によって特有の意味を持つものです。従来の質問紙や統計モデルでは、「それは人種による差別か、性別による差別か」といったように二分法で問いかけられることが多く、インターセクショナリティの経験を適切に捉えることが困難になります。
こうした問題意識のもとで、Coleはインターセクショナリティの視点を研究プロセスの各段階(仮説の生成、サンプリング、測定項目の操作化、分析、結果の解釈)においてどのように取り入れるかを、以下のように三つの問いと結びつけて整理しています。
| 研究段階 | 問い①:このカテゴリーには誰が含まれているのか? | 問い②:不平等はどのような役割を果たしているのか? | 問い③:どこに共通点があるのか? |
|---|---|---|---|
| 仮説の生成 | カテゴリー内の多様性に注意を払う | 文献レビューで不平等の社会的・歴史的文脈に注目する | 共通点を発見するために仮説検証型ではなく探索的研究になることもある |
| サンプリング | これまで無視されてきた集団に焦点を当てる | カテゴリーに当てはめることは、権力や資源へのアクセスに不平等をもたらす区分であることに留意する | 社会的・制度的権力に共通の関係性をもつ多様な集団を含める |
| 評価設計 | 対象集団の視点から測定尺度を開発する | 比較研究では、差異が個人レベルではなく構造的不平等に由来するものと捉える | 社会的カテゴリーを個人特性ではなく制度的・実践的構造として捉える |
| 分析 | 集団内の多様性に注目し、場合によっては集団ごとに個別に分析する | 共通点と差異の両方を検討する | 差異に限定せずに関心を向ける |
| 結果の解釈 | どの集団の結果も「普遍的」あるいは「規範的」な経験として解釈しない | 差異は集団の構造的位置に基づいて解釈される | 共通点が見られた場合でも、集団間の微妙な差異に配慮する |
このように、インターセクショナリティの視点は研究設計や方法の各段階において、既存の「前提」や「常識」を揺るがすものであり、単なる分析ツールではなく理論的視座そのものの転換を意味します。Coleは、心理学者がこうした枠組みを積極的に取り入れ、データの「見方」自体を更新していくことの重要性を強調しています。
最後に インターセクショナリティを反映した研究例として取り上げられていたShih, Pittinsky, & Ambady (1999)の研究を紹介します。以下の研究は単に交互作用項をモデルに含めるという方法論的操作にとどまらず、カテゴリーの意味を文化的・状況的に再構成しながら測定しています。また、複数の社会的位置が同時に存在するというインターセクショナリティの原則を、操作的に再現(プライミング)することに成功した例として言えます。
研究内容:
アジア系アメリカ人女性を対象に、交差するアイデンティティ(人種と性別)が認知的パフォーマンス(特に数学成績)に与える影響を実験的に検討した研究。
方法:
・実験群に対して、事前に「アジア人性」または「女性性」をプライミング。
・プライム内容によって数学成績に違いが生じるかを検証。
主な発見:
・女性性をプライミングされた群はパフォーマンスが低下。
・アジア人性をプライミングされた群は成績が向上。
・同様の実験をカナダ・バンクーバーの参加者に行ったところ、アジア人性プライムの効果は再現されなかった。これは文化的文脈の違いが影響していると考察されている。
この研究の意義:
・同一の人物にとって、「アジア系であること」と「女性であること」という複数のアイデンティティが同時に存在し、状況に応じて心理的影響を与えることを実証。
・交差するカテゴリーを静的な統計変数としてではなく、文脈依存的なプロセスとして扱った点で、インターセクショナリティの視点を活かした研究とされている。
結論:インターセクショナリティは誰にとっても必要な分析枠組みである
論文の結論部分でColeは、交差性は単にマイノリティの研究にのみ適用されるものではなく、すべての心理学研究者にとって不可欠なパラダイムであると強調します。性別、階級、人種、セクシュアリティが交差し合うことで構築される人間の行動や心理的経験を理解するには、単一の軸ではなく交差する視点が必要であり、これは研究の正確性と妥当性の向上に直結するものです。
感想
インターセクショナリティを実証研究に適応することを考えると、無意識に質的研究を行って質的データで社会的アイデンティティに関わる複雑さを掬い上げることをイメージしてしまう気がします。Coleは質・量の二分法を超えて、すべての実証研究にインターセクショナリティを研究パラダイムとして導入することを提案しており、非常に重要な指摘だと思います。この論文で提案されている3つの問いのフレームワークを意識しながら、論文で紹介されている様な具体的な実証研究に触れて、自分の研究をいかにインターセクショナリティを意識したものに変えるかを考えていきたいと思います。