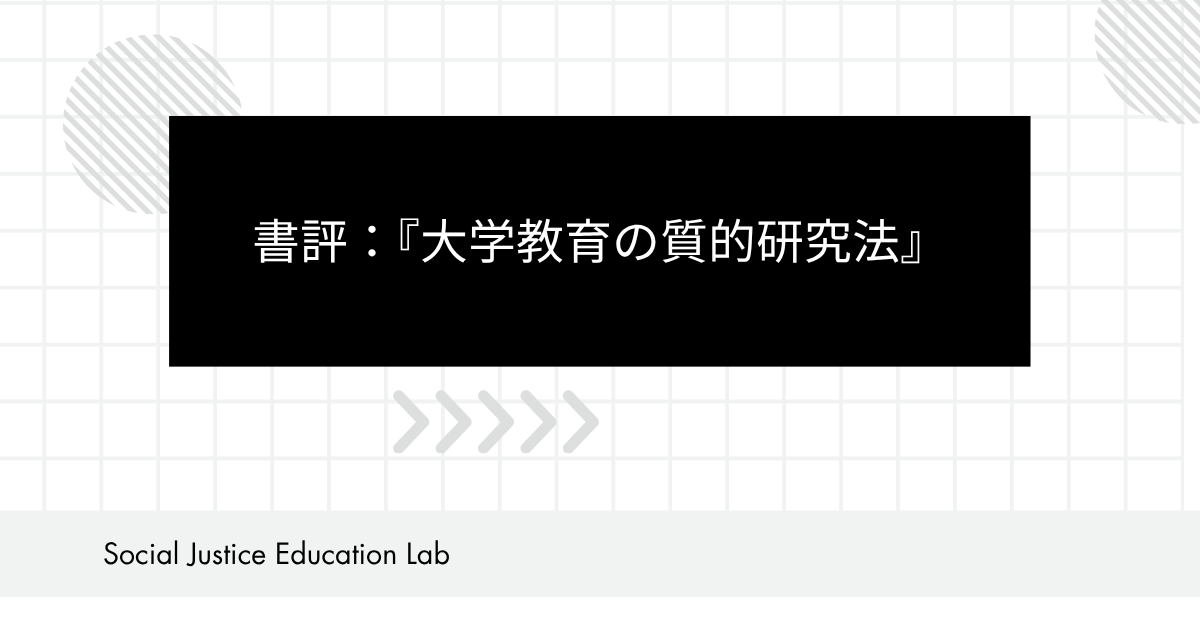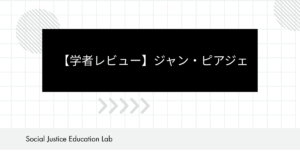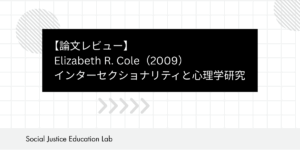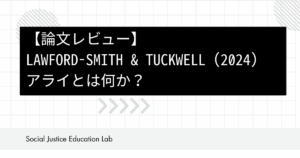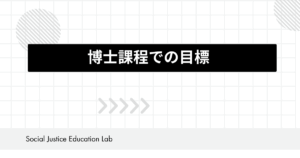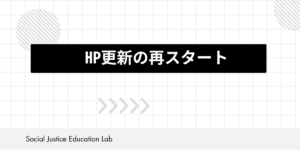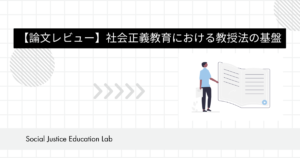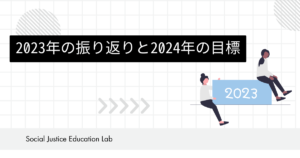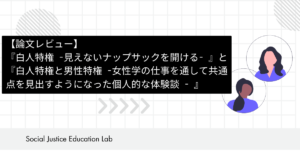今回は『大学教育の質的研究法』という本の紹介をしたいと思います。現在、この本の翻訳・出版を機に始められた著者の山田先生、河井先生、新見先生が主催されている研究会に参加させていただいています。研究会に参加する前に、そして参加しながら『大学教育の質的研究法』を読んできたので、一旦自分の考えをまとめておきたいと思いました。
『大学教育の質的研究法』はNegotiating the Complexties of Qualitative Research in Higher Education: Essential Elements and Issues, Third Edition (Susan R. Jones, Vasti Torres, and Jan Arminio, 2022) の全訳です。著者3名は北米の高等教育研究では著名な研究者であり、本書はその3名の著者の経験に裏打ちされた、高等教育を対象に質的研究を行いたい研究者にとっての格好の入門書となっています。
本書の特徴の一つは、質的研究をこれから始める学生・研究者の視点に立って書かれていることです。質的研究には様々なアプローチが存在しており、初学者は何から初めていいかわからず困ってしまうことがしばしば起こります。試しにグラウンデッド・セオリーの本を手にとってみたり、エスノグラフィーの本を読んでみたりするけれども、最初の一歩をどう踏み出していいかわからない・・・。この本は、第1章で学生・研究者の「切実な関心」を明確にすることを呼びかけています。そして、切実な関心を明確にした上で、その関心はどのような世界観(研究パラダイム)の中で考えるのが適切なのか、どのような概念的な枠組みの中に位置付けられるのかを問いかけ、リサーチ・クエスチョンの設定まで導いてくれます。特に、世界観(研究パラダイム)の説明は日本の研究法の本だとあまり説明されることが多くないため、初学者にとっては(少し小難しく思えるかもしれませんが)ありがたいはずです。
本書のもう一つの特徴は、マイノリティが生み出す知のあり方へのリスペクトです。北米の高等教育論、特に大学キャンパスをフィールドにした学生支援と呼ばれる分野の研究では、キャンパスの中で抑圧される傾向にあるマイノリティの学生の置かれた現実を明らかにする研究が盛んです。初学者がそのような研究を行えるようにサポートすることが念頭に置かれて、本書は執筆されているように感じました。例えば、第二章の「理論的視点」の節では象徴的相互作用論のような理論に並んで、クィア理論、批判的人種理論、ラテン系の批判理論(LatCrit)、先住民の批判理論(TribalCrit)など様々なマイノリティの立場から前提となっている規範を批判する理論が説明されています。また、本書を通じて紹介される研究の具体例も、交差性が前提となった批判的な理論を基にした研究ばかりです。アファーマティブ・アクション以降、高等教育における多様性の実現に研究領域として真摯に取り組んできた北米の高等教育論の本気さを感じられるという意味でも、本書は大きな価値があると思います。
私が考える本書の最後の特徴は、研究倫理に大きくページを割いているところです。本書全体で研究倫理への言及がありますが、特に第8章「研究者の倫理的責任」、第9章「質の高い研究者の義務」などで詳しく論じられています。先述のように、大学キャンパスをフィールドにしたマイノリティの学生に接する研究が想定されているため、研究者の立場性や再帰性という概念に大きな注意が向けられています。日本でも、各大学の倫理審査委員会での検討を通した上で研究を行うことが一般的になりつつありますが、害を与えないことは当然とした上で、善を行うという責務とどう向き合うかということが問われています。
以上のような特徴を持つ本書ですが、いくつか気になる点もあります。例えば、認識論の説明の中で実証主義の説明の後は、基本的に解釈主義的な認識論についての説明が続きます。ただ、量的研究と質的研究を組み合わせた混合研究も盛んに行われる分野であることを踏まえると、両者の間に位置する批判的実在論についての説明も必要に思えます。また、第4章の「方法論的アプローチ」についても網羅性があるのか、説明されているアプローチのレベル感は揃っているのか、若干疑問に感じました。とはいえ、それらの点は上に挙げた魅力を減じるようなものではありません。質的研究の奥深い世界を一冊だけで全て切り拓くのは無理な話だと思うので、他の方法論を扱った書籍を参考にして補いつつ、本書に当たるのが良いと思います。